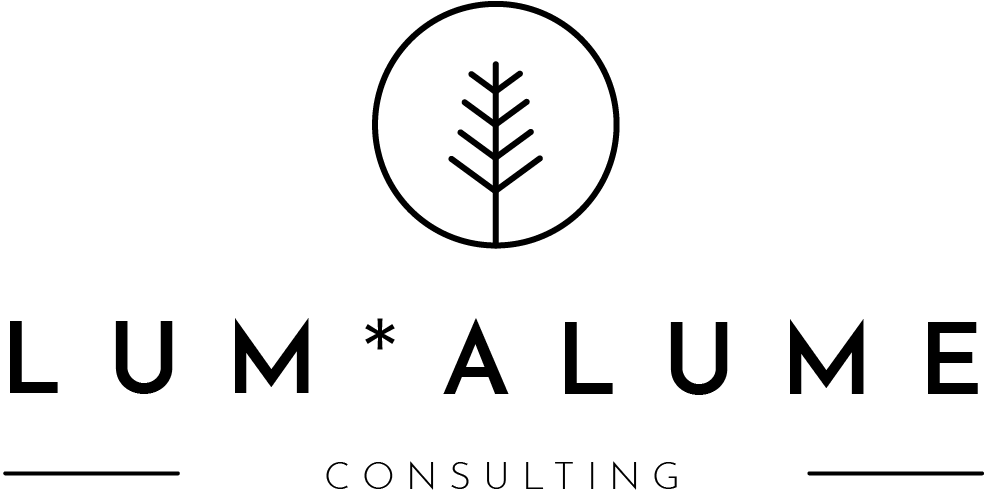女性が管理職になりたがらないのはなぜ?心理的・環境的要因とその解決策

企業でしばしば見られる「女性が管理職になりたがらない」という現象。その背後には、意欲の欠如ではなく、複雑な心理的・環境的制約が横たわっています。本稿ではその要因を整理し、味の素や伊藤忠商事の実例を交えながら、経営者や人事担当者が取り組むべき解決策を提示します。
心理的なブレーキ:自己効力感の低さとロールモデルの欠如
まず大きな要因として、自分には管理職が務まらないのではないかという「自己効力感の低さ」が挙げられます。内閣府の調査でも、女性は男性に比べて自らの能力を過小評価する傾向が明らかになっています。さらに、周囲に女性管理職が少ない職場環境では「自分もその立場になれるのか」という不信感が募り、挑戦意欲を削いでしまいます。
こうした課題に対し、味の素は2020年に「AjiPanna Academy(アジパンナ・アカデミー)」を立ち上げ、管理職登用を見据えた育成プログラムを整備しました。女性が身近にロールモデルを持ち、管理職像を現実的に描けるようにした点は、心理的ハードルを下げる効果を発揮しています。
環境的障壁:長時間労働と家庭負担のアンバランス
心理的要因に加え、環境的な障壁も大きな影響を及ぼしています。日本の職場文化では長時間労働が根強く残り、加えて家庭や育児の負担が依然として女性に偏りがちです。OECDの調査によると、日本の女性は男性の2倍以上の時間を無償労働に充てており、管理職として求められる働き方への抵抗感を抱きやすい状況があります。
味の素はこうした課題に対応するため、コアタイムのないフレックスタイム制やテレワークの導入、さらに退社時間の繰り上げなどを進めました。働き方そのものを見直すことで、管理職を目指す女性が無理なく挑戦できる環境を整備しています。
組織文化の無意識バイアスと昇進の機会偏重
また、昇進機会における見えない壁として「アンコンシャス・バイアス」も存在します。「管理職に向いているのは男性」「女性は家庭を優先するもの」という固定観念が、無意識のうちに評価や登用に影響を及ぼすのです。
伊藤忠商事では、この問題に対処するために取締役会レベルで「女性活躍推進委員会」を設置し、女性執行役員登用のための別枠選考ルールを導入しました。その結果、2024年4月には女性執行役員が5名に増え、役員比率は21%に達しました。さらに2025年度末には30%超を目指す方針を掲げており、制度設計によって無意識バイアスを克服しようとする姿勢が見て取れます。
解決策:意欲と制度の両面からの支援
こうした状況を改善するためには、個人の意欲喚起と制度的支援を両輪で進める必要があります。まずは、メンター制度や女性管理職によるロールモデル提示を通じて「自分にもできる」という感覚を強化することが求められます。味の素の「AjiPanna Academy」のように、管理職登用と育成プログラムを組み合わせる取り組みは有効な手段といえるでしょう。
同時に、フレックスタイムやテレワークといった柔軟な勤務制度を管理職にも適用し、家庭との両立を可能にする環境整備が欠かせません。また、昇進プロセスを透明化し、公正な評価を担保することも重要です。伊藤忠のようにスポンサー制度や別枠ルールを導入して実戦的な機会を与えることは、女性の登用を後押しする有効な手段になります。最終的には、取締役会レベルでのガバナンス強化や社外取締役の関与を通じて、施策の実効性を高めることが組織全体に求められます。
成果と将来への期待
味の素や伊藤忠商事の事例は、意識改革と仕組み改革の両輪が揃って初めて女性の管理職比率やキャリア自信が向上することを示しています。女性の活躍は単なる社会的課題にとどまらず、組織のレジリエンスを強化し、イノベーションを促進する力となります。今後も本気で改革に臨む企業が増えれば、多様性が組織競争力を押し上げる「次世代経営」の実現が加速するでしょう。